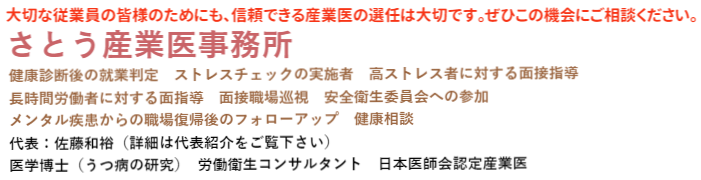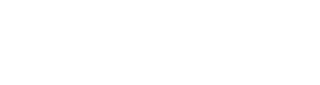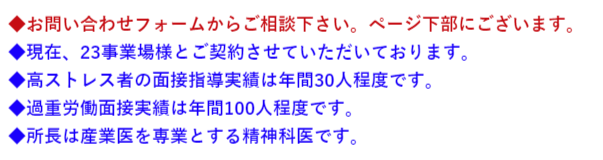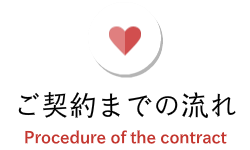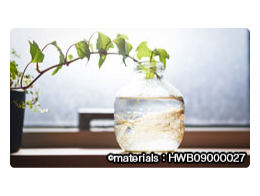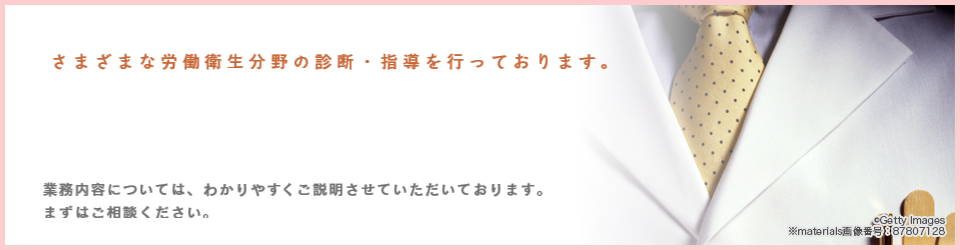ご契約の流れ
Procedure of the contract
Step 1 : お問合せをお願いいたします
・お問合せフォームまたはメールでお問合せ下さい。
・2営業日中に当事務所からご連絡をいたします。365日24時間受け付けております。
Step 2 : 御社を訪問して労働衛生状況を診断いたします
・当事務所代表産業医が御社を訪問して、人事労務ご担当者様からお話を伺って、現状の労働衛生状況を診断し、また、職場巡視場所を確認させていただきます。
・その際に、御社において困った事例や問題点が既に発生しているようでしたら、お気軽にご相談下さい。解決までのアウトラインをご提案いたします。
・また、どのような点に力を入れていきたいのかをお教えください。
*労働衛生状況の診断、ご相談は無料です。
Step 3 : サービス内容のご提案・見積書の作成いたします
・現状の労働衛生状況及びご相談内容から労働衛生サマリー(現状の御社の労働衛生状況の診断書)を作成いたします。
・これらを踏まえて、当事務所から業務内容及び訪問スケジュールのご提案を行い、業務内容・訪問時間数・訪問日時をご協議させていただき、見積書を作成いたします。
*労働衛生サマリーの作成、訪問スケジュールのご提案、お見積りは無料です。
1)訪問時間数は業務内容により決めさせていただいております。
2)報酬額は訪問時間数及び訪問日時により決めさせていただいております。
3)報酬額は秋田県医師会が定めた標準月額を基に定めております。
4)事業規模や従業員数によらず上記の方法で料金を決定します。
Step 4 : ご契約をお願いいたします
・ご契約いただける場合、業務委託契約書を取り交わします。
*ご契約後に衛生委員会の進行例を差し上げております。
Step 5 : サービスを開始いたします
・料金は契約月ではなく、サービス開始月から発生いたします。
・ご契約頂いた月から産業医業務を開始することも可能です。
1)毎月、産業医業務実績報告書、職場巡視結果報告書を無償で発行しております。
2)その他、適宜、面談記録、産業医意見書等を無償で発行いたします。
3)見積書、請求書、領収書が必要な場合、発行いたします。
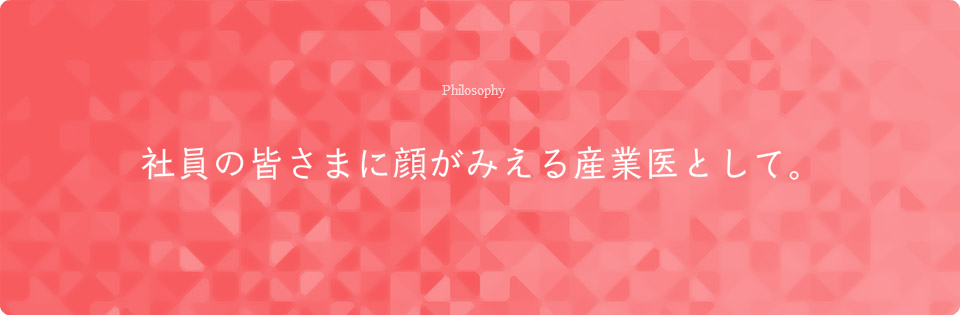
今日だけでなく、明日も、未来も。
さとう産業医事務所は、変化を通じて
サスティナブルな産業保健サービスを心がけます。
うつ病等の気分障害患者数は、5大疾病のトップに躍進し、がん患者数の約2倍となりました。平成9年度以降は労働者の約6割が仕事で強い不安やストレスを感じながら働いています。平成26年度の自殺者数は約2万5千人で、その約3割が労働者で占められています。精神疾患による労災請求件数及び労災認定件数は過去最高を更新するなどここ数年は右肩上がりに増加しています。そのため、メンタルヘルスケア分野において安全配慮義務を怠った場合、事業者さまはメンタルヘルスケア対策の責任を問われる傾向にあります。このような社会的背景から、メンタルヘルスケアがリスクマネジメントの要であるという考え方が広く浸透してまいりました。しかしながら、事業者さまが望んでいらっしゃるにもかかわらず、十分なメンタルヘルスケア対策を講じることができない事業場は少なくございません。
これには3つの大きな理由が考えられます。最初の理由は、精神科を専門としている産業医数の絶対的な不足です。「産業医」のみで糧を得ている医師は産業医全体の0.2%に過ぎず、その中での精神科医の割合については統計学的な資料すら存在していません。ゆえに、メンタルヘルスケア活動の大部分は非精神科の嘱託産業医によって担われているという現実があります。しかしながら、メンタルヘルスケア対策において、非精神科の嘱託産業医が一次予防(ストレスチェック制度、セルフケア、ラインによるケア等による発症予防)へ関与することはその専門性の欠如のためほとんど行われておりません。二次予防(疾病の早期発見とその対応)においては、精神医学的な症状評価に自信を持てず、疾病性の有無を判断することに困難を感じていらっしゃいます。三次予防(主として職場復帰支援)においては、精神科主治医の所見に疑問を持っても合理的に抗弁する術を持ないため、主治医の診断書通りに職場復帰を認めてしまう場合も少なくありません。
次の理由は、開業医さま等が忙しい日常診療の合間に産業医活動に従事している非専業産業医であることです。非専業であるため、メンタルヘルスケア等に関する知識を得る時間や経験を積む時間が限られてしまうのです。産業医は法令(法、施行令、規則)に基づいて職務を遂行するのですが、法令に基づいて産業医業務を実施するためには、多くの時間と労力を要します。また、事案によっては、事業場の実情を把握し、管理監督者や人事労務担当者と協力し、多方面から情報収集をしたうえで総合的に判断して事業者へ意見を述べることや精神科主治医と連携すること等が必要な場合もあります。これらについては時間と手数を掛けて経験を積み重ねることによってのみスキルアップが可能となるものなのです。
最後の理由は、臨床医学による判断(主治医=通常の医師が行う判断)と産業医学による判断(産業医が行う判断)が大きく異なる場合があることです。例えば、主治医による職場復帰可能の判断基準は、「病態が安定している」という状態ですが、産業医による職場復帰可能の判断基準は、「就労規定で定められた業務時間に勤務ができる」という状態です(注:必要に応じて一定の配慮は行いますが、特定の労働者に偏った配慮とならないよう注意する必要があります)。非専業産業医が、主治医の立場からではなく、産業医の立場から様々な判断を行うことには困難を伴うと考えられます。
これらの包含する諸問題を解決するためには、精神科治療のバックグラウンドを持った産業医が専業として産業医活動に従事する必要があると考えられます。当事務所は、豊富な精神科の専門的な知識と経験及び労働衛生の現場における知識と経験をもつ専業産業医として、メンタルヘルスケア対策を含む労働衛生分野における多種多様のサービスを提供しております。